2014.08.25 [ クロロフィル通信 | オフィスだより ]

今年も本社前の花壇にサンパチェンスを植えました。
暑い中でも、鮮やかな花を咲かせています。
でも、このサンパチェンスが植えられるのを待っていたのは私たちだけではありません…

探してみると、やっぱり大きく太ったセスジスズメの幼虫がいました。背中の目玉の模様がこちらを見ているようで、頭を丸めているとまるで蛇みたいです。
終齢幼虫は人差し指くらいある大型の蛾の幼虫で、サトイモ、コンニャク、ブドウにも発生します。コナガのように大量発生はしませんが、体が大きい分たくさん食べるので、放っておくと数匹いるだけでも作物は丸坊主です。防除するには早めに発見し、取り除かなくてはいけません。

ちなみに成虫はこんなかんじです。スズメのように活発に飛び回ること、背中の一本線が名前の由来だそうです。
サンパチェンスについた幼虫は、丸坊主にされる前に取り除きました。でも私は殺すのは苦手なので……(--;)
その幼虫をどうしたかは秘密です。
≪肥料農薬担当≫
2014.08.23 [ クロロフィル通信 | オフィスだより ]
豊橋技術科学大学のオープンキャンパスで開催された「植物工場と6次産業化」という講演を聴きに行きました。
三枝教授の講義「ITで拓く 植物工場と6次産業化」に引き続き、実際の植物工場と6次産業化を行っている企業、農家の事例発表がありました。
その中でのトヨハシ種苗研究農場にて研修生として勉強され、ミニトマト栽培をされている冨永氏の発表では、お父様からの長年の経験の基づく栽培技術と最新の環境制御技術やITを駆使した栽培管理を上手く融合させた発表はすばらしいものでした。

企業の閉鎖型植物工場の取組と農家の太陽光利用型植物工場の最前線がどうなっているのか良くわかる講演会でした。
種苗部
2014.07.18 [ クロロフィル通信 | オフィスだより ]
今年度最後のスイートコーンの圃場見学会を実施しました。
種苗メーカーの育種担当の方から品種についての細かな説明をしていただきました。
参加していただいた農家さんからは熱心な質問、そして他の品種を含めた試食会もありました。
来年から本格販売をする予定のサカタのタネのスイートコーンの新品種が中心の見学会でした。
今回の新品種のテーマは、風で倒れない、収穫適期が長い(在圃性)です。
お客様の圃場やトヨハシ種苗の研究農場での品種の試作を通じて、その地域にあった品種をお客様に提案してゆくことになります。

2014.04.11 [ クロロフィル通信 | オフィスだより ]
桜も散り、やっと暖かさを感じられるようになりました。
今年の冬は寒かったですね~。
トヨハシ種苗でも15名の新入社員が加わり、フレッシュな雰囲気となっております。
季節は4月で新しいスタートの時期ですが、まだまだ田原市のキャベツの収穫は続きます。
生産者の皆様におかれましては、くれぐれも無理をなさらぬように、ご自愛くださいませ。
今作は10月の2回の台風と10月中旬~下旬の大雨、11月の急激な冷え込みで、夏蒔きのキャベツにとっては受難の年だったと思われます。
特に4月どりの寒玉では、生育が遅れ外葉が出来ず、結球の葉の枚数が少なくなることで芯の押さえが効かず、芯伸びが助長されている状況です。
特に4月収穫の寒玉キャベツは、播種の適期が非常に短く、また、定植期が台風や秋雨により天候が不安定で、キャベツの出来が天候や秋の冷え込みの早い遅いに左右されてしまう、生産者の方が大変ご苦労されている大変難しい作型です。
現在私共では、4月どりのキャベツのご苦労を少しでも改善できる品種を現在試験中です。
先日も試験栽培頂いた方の畑を見させていただきました。
生産者の方の腕ももちろん良いのですが、試験品種も特性を発揮しており、なかなか良い状況でした。

この品種はすぐに商品にできるわけではありませんが、生産者の皆さんのお役にたてる品種ではないかと期待が膨らんだ一日でした。
田原営業所 坂神
2014.04.01 [ クロロフィル通信 | オフィスだより ]
先日、『災害に強い施設園芸を目指す研修会』に参加してまいりました。

平成23年9月に来襲した台風15号により、静岡県西部地域を中心にハウス施設に甚大な被害が出ました。
このため静岡県内の関係機関にて『 災害に強い施設園芸を目指す研究会 』が発足し、台風等の強風対策技術を普及させるため、今回の研修会が開催されることとなったのです。
被害が出る前の対策に役立てる事を主眼とし、補強方法の事例を中心に行なわれました。
農研機構の森山研究員の講演では、強風対策だけでなく、今年の北関東の大雪被害の説明もあり、ガラス温室等の屋根型でもガラスが割れ、倒壊したという現場説明をお聞きし、改めて自然災害の恐ろしさを教えて頂きました。
当社は静岡県内で行われた補強方法を中心に施工事例・部材金額を説明し、静岡県農業振興課の職員の方は施工方法の小型模型を作成されました。
模型に触れて動かす事で、補強方法の違いによる揺れ方の違いが良く分かり、大変良い展示でした。

地域単位での研修会開催依頼の話や、いかに実際に現場に浸透させるかなど、今後の大きな課題や災害対策の進め方について話し合うことができました。
社長室
2014.03.07 [ クロロフィル通信 | オフィスだより ]
ちょっと暖かくなってきたなと思っていたのですが、また寒くなってきてしまいましたね。。
さて、先日のブログにも掲載されましたが、東京湾に面した晴海客船ターミナルホールにて、第35回施設園芸総合セミナーが開催されました。

『 施設園芸新技術とトマト高収益施設園芸の実現を目指して 』 をテーマに掲げ、参加者が1日目に400名超え、2日目には500名を超えて立ち見が出るほどの大盛況となりました。
このとき関東地方では大雪の影響により、ハウスの倒壊等の被害が多く発生してしまったため、参加したいが見送った方がさらに多くいらっしゃると事務局の方からお聞きました。
改めてトマト栽培における多収栽培技術が大変注目されている事が感じられました。
当社も展示ホール機器資材展の一角にて、環境制御機器の一環としてCO2当番を展示し、濃度施用の重要性を説明させていただきました。

「統合環境制御には哲学がある」、
重油の高騰があり施設園芸には大変厳しい経営環境ですが「経費削減は利益率の改善にはつながるが、事業の成長には直接貢献しない」、
「環境制御機器等の必要な投資を行う事が、施設園芸の継続的な成長につながる」
という、誠和株式会社の斉藤氏の力強い説明をお聞きすることができ、改めて環境制御機器の重要性を実感したセミナーでした。

社長室
2014.01.23 [ クロロフィル通信 | オフィスだより ]
受付の内藤さんが、梅の枝を生けてくれました。

たくさん蕾が生っています♪
枝をよく見ると、元々生えていた部分は茶色に、新しく生えてきた部分は緑色にくっきり染まっています。
小さな剣山から大きく広がる枝は、一本一本は細いですが、力強く生えているように見えます。

2月になれば、枝先まで花を咲かせて今度は可愛らしく変身することでしょう(^^)
寒さに負けず開花の時を待つ梅を見ると、パワーをもらいますね!!
受付に飾ってあります。お越しくださいます際は、どうぞご覧ください。
編集室
2014.01.10 [ クロロフィル通信 | オフィスだより ]
かねてより株式会社デンソーさんと取り組んでいるProfarm事業について、社内向けの見学会と勉強会が開催されました!!
Profarm-controllerという制御機器を使って実証試験を行なっている、弊社研究農場の実証ハウスを見学し、使用方法や事業の概要を勉強しました。



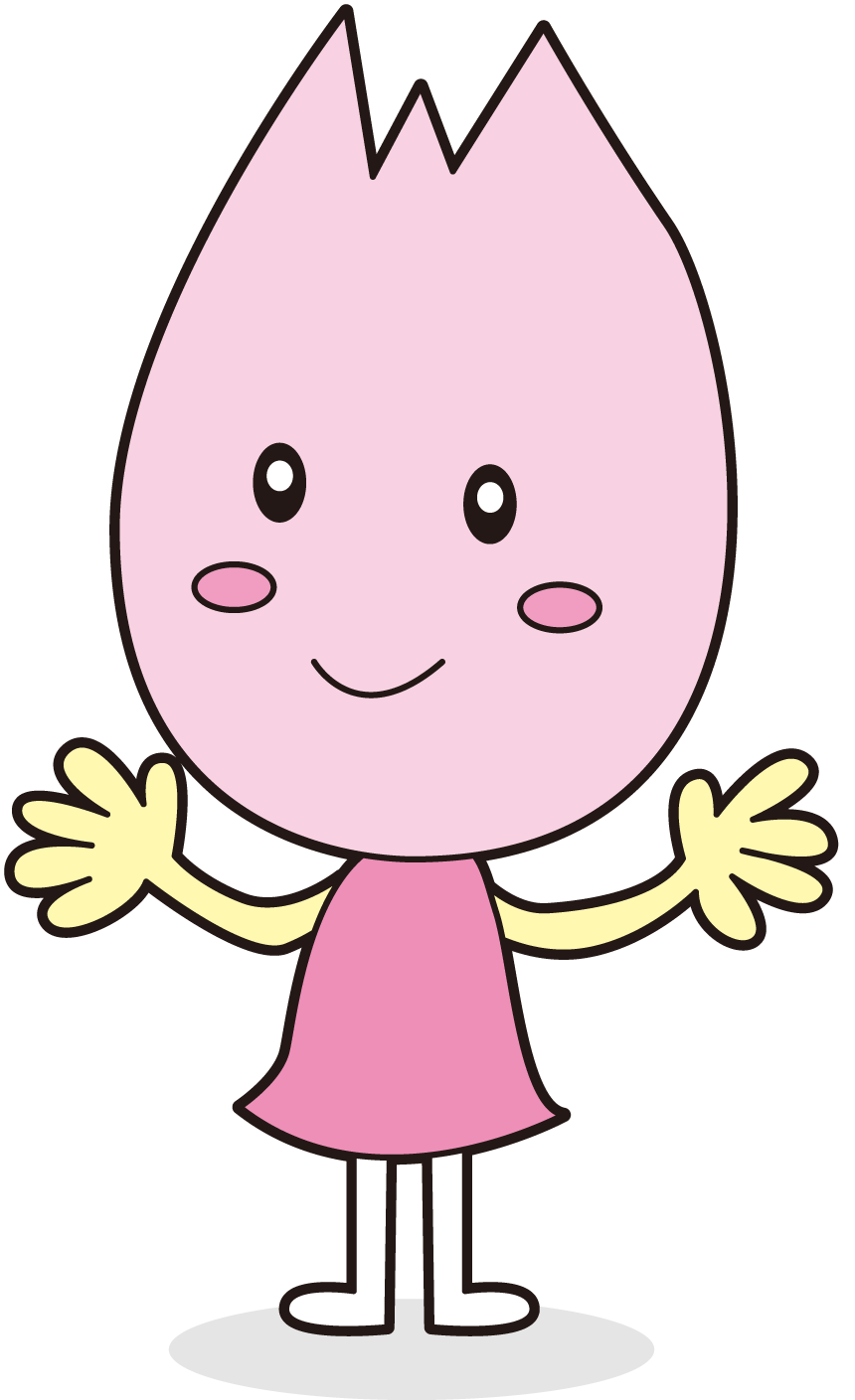
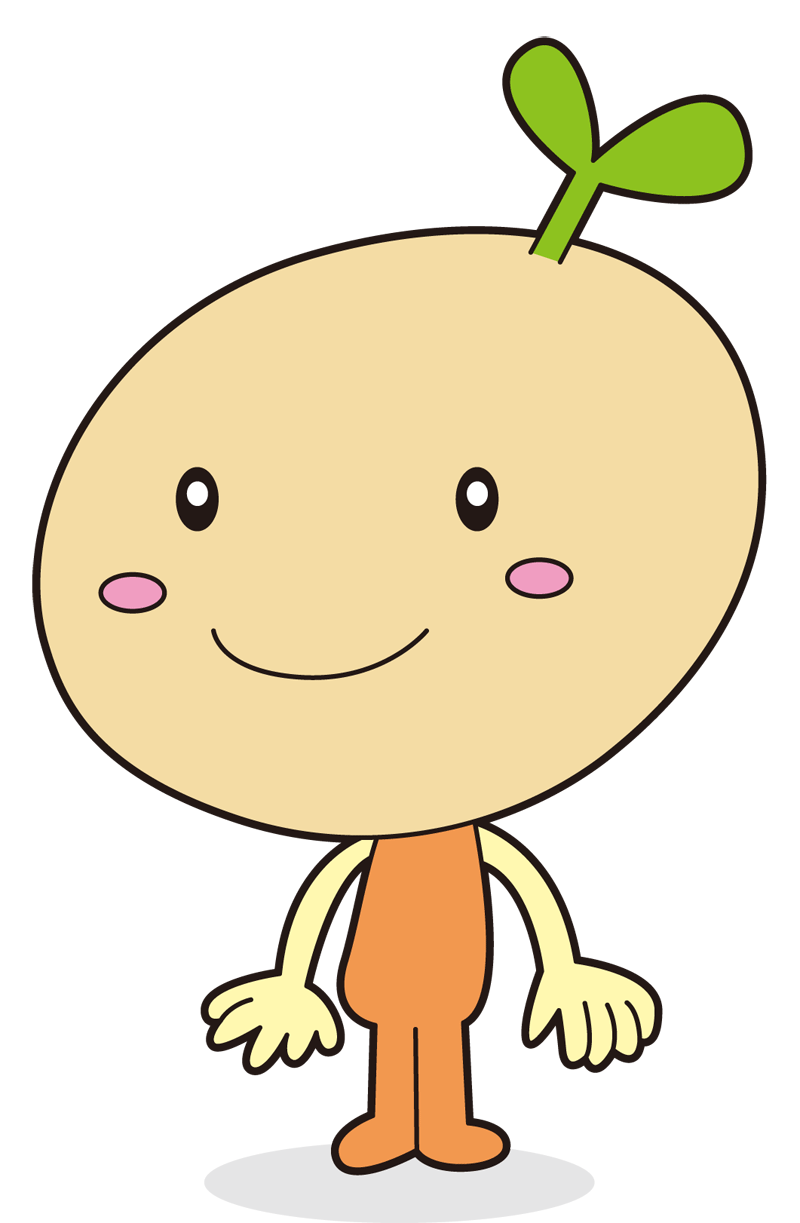
Profarm-controllerは、
温度にこだわった管理機能や
使いやすさを追求しています。
株式会社デンソーさんの持っている製品品質と、弊社の栽培ノウハウを融合させた事業第一弾の商品ということで、今までにないアイデアが満載だと思いました。
販売段階ではありませんが、収量アップへの貢献に期待が高まります!!
収量アップの実現に向けて、生産へのよりよい活かし方を日々考えていきます。
入社3年目 S
2013.12.10 [ クロロフィル通信 | オフィスだより ]
弊社のオリジナル商品の1つである「CO2当盤」の社内勉強会に参加しました。
販売当初からの変更点や使用のポイントなどを、実物を稼働しながら学ぶことができました。

CO2当盤は、CO2発生機にCO2の燃焼などの信号を送る制御盤です。
 CO2当盤カタログ
CO2当盤カタログ
おかげ様で、導入実績は約600台となりました。
秋・冬が導入シーズンであり、今年も多数ご注文いただいています。
メンテナンス面を含め、お客様により効率的にお使いいただけるよう、社内勉強会が定期的にあります。
勉強会では、課員の皆さんが現場に活かすために努力されている姿が、まじまじと伺えます。
今回の勉強会も内容濃く、あっというまに時間が過ぎていきました。

今後も、お客様のもとへ情報・商品・サービスをあらゆる形でお届けできるように、切磋琢磨して頑張ります!!
企画開発室S.N
2013.12.06 [ クロロフィル通信 | オフィスだより ]

昨年度より、トマトの環境制御による増収技術検討会として、
愛知県農業試験場 ・ 愛知県東三河農業研究所 ・ JAあいち経済連 ・ トヨハシ種苗、の共同研究により取り組んでいます。
平成25年度の一回目として、JA・トマト部会長・普及所の関係者を集め、JAあいち経済連支援センターにて、中間報告会が開催されました。
来年7月の収穫終了までに、一反 40トンの収穫を目指しており、穂木は昨年の結果から「りんか409」を採用、台木は「がんばる根3号」及び「スパイク23」を比較して試験を行うこととなりました。
使用培地は
・ ロックウール培地の連続発砲ベット区
・ ココヤシ培地のココバック
・ トマトコンテナ培土のドリームボックス
を使用して、EC管理・かけ流し方式の養液栽培システムにて行います。
高軒高のハウスなので、暖房だけでなく、炭酸ガス施用・湿度コントロール機能を有しています。
施設トマトにおける安定多収生産を実現する事により、農家さんの経営安定と生産振興を図る事を目的に進めている取組です。

社長室













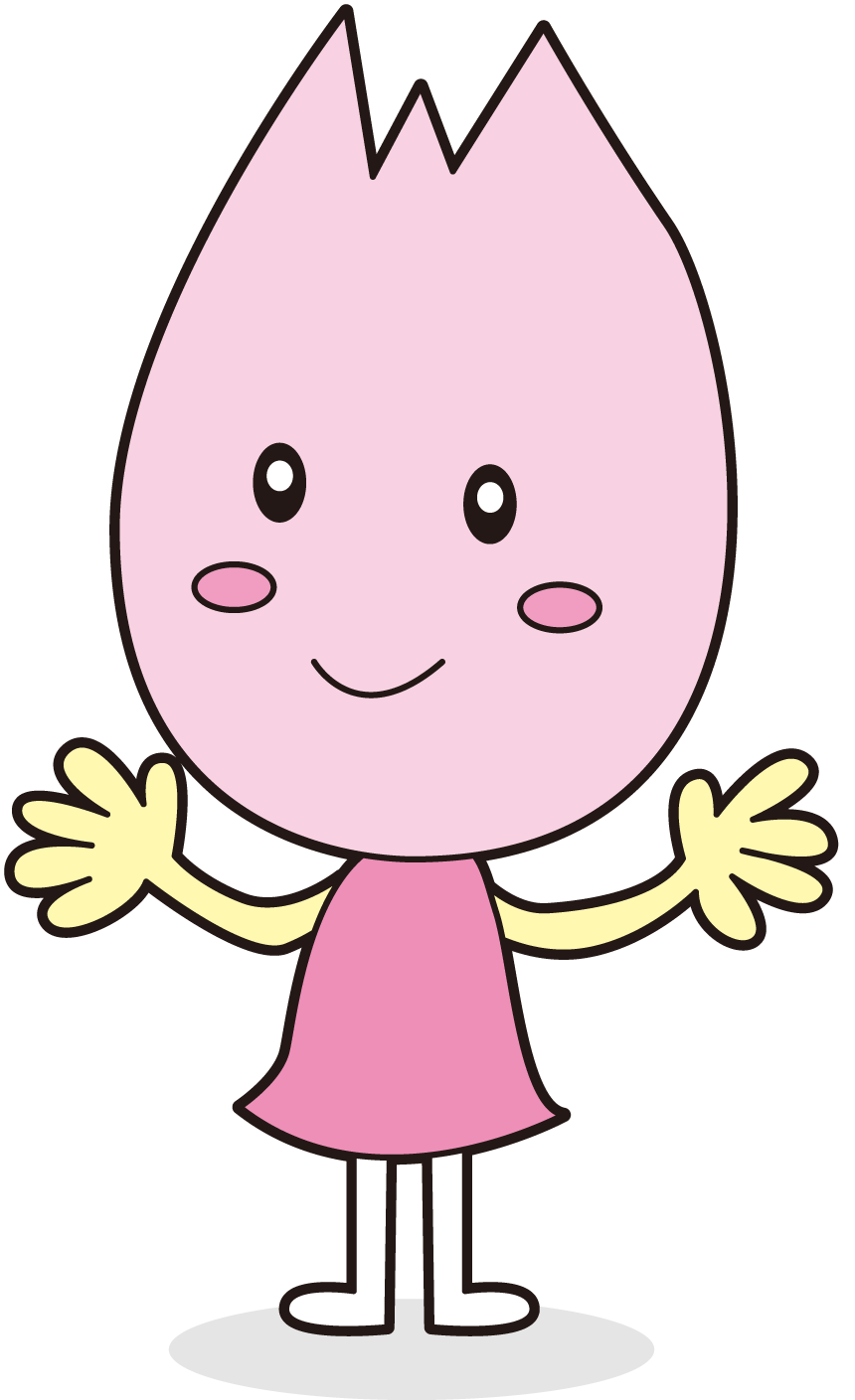
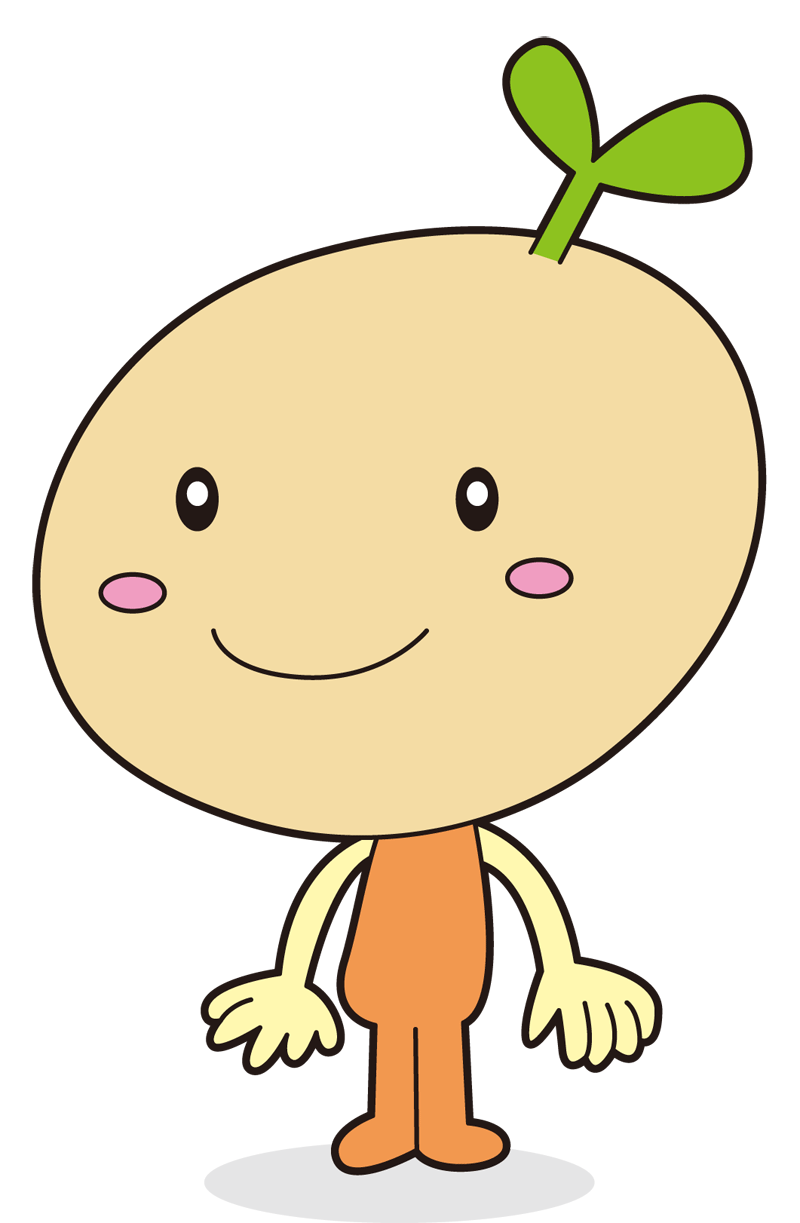


 昨年度より、トマトの環境制御による増収技術検討会として、
昨年度より、トマトの環境制御による増収技術検討会として、